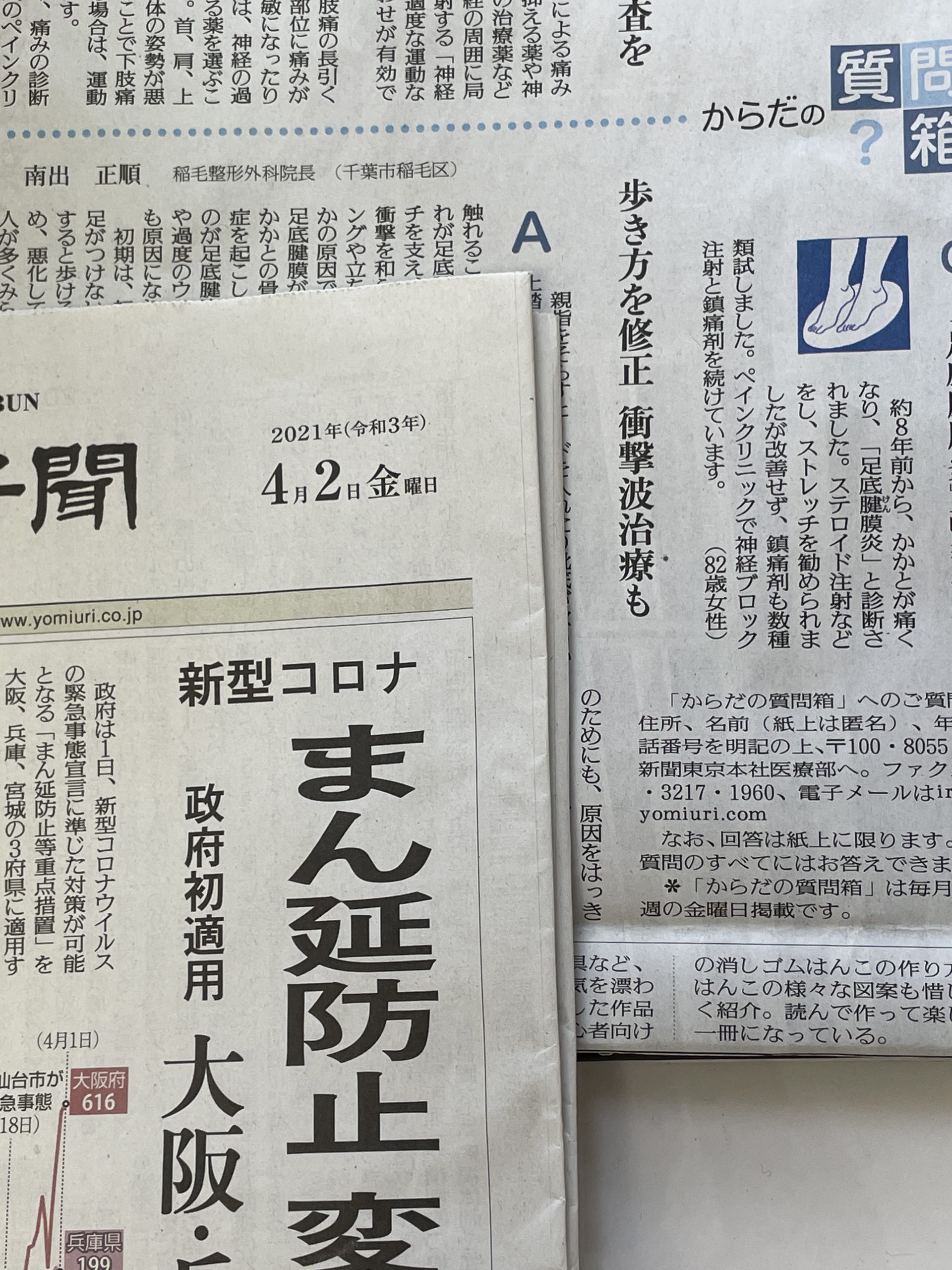ランニングは健康に良い運動ですが、やりすぎると足の骨にダメージを与える可能性があります。ランニングによる疲労骨折とは、同じ部位に小さな力が繰り返し加わることで、骨に亀裂が入ったり、折れてしまったりする状態です。ランニングでの疲労骨折は、主に脛骨(すねの骨)、中足骨(足の甲の骨)、腓骨(すねの外側の骨)などに起こりやすいです。
疲労骨折の原因は、過度のトレーニング、不適切なシューズやフォーム、栄養不足やホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。疲労骨折の症状は、運動時や圧迫時に痛みを感じることが多く、患部が腫れたり硬くなったりする場合もあります。疲労骨折はレントゲン検査やMRI検査などで診断されます。
疲労骨折の治療法は、原則として安静にすることです。原因となった運動を中止し、患部に負担をかけないようにします。必要に応じて松葉杖やギプス固定などを行います。また、栄養バランスの良い食事やサプリメントを摂ることも大切です。完治までには数週間から数ヶ月かかる場合があります。
疲労骨折を予防するためには、以下のことに注意しましょう。
・トレーニング量や強度を徐々に増やす
・シューズや靴下を足に合わせて選ぶ
・ランニングフォームを正しくする
・地面が硬すぎない場所で走る
・ストレッチや筋トレで筋力や柔軟性を高める
・カルシウムやタンパク質などの骨を強くする栄養素を摂る
・女性ホルモンのバランスを整える
ランニングは楽しく健康的な運動ですが、無理をしないようにしましょう。自分の体調やレベルに合わせてトレーニングを行い、疲労骨折を予防しましょう。